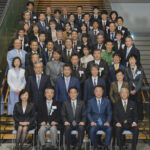【代表廣瀬の特別連載④】SHIZQの源流をたどる <希望をデザインする神山>
2023年6月8日
旅の最終日、廣瀬は、The smashing pumpkins(スマパン) を思い出し、昔のように聴きながら走った。
当時、スマパンの曲に重ねていたのは、スティード400のエンジン音。
長髪の「赤パンのジェロ」は、風に髪を靡かせて走った。
今は、ハーレー独特の、太いエンジン音が、スマパンにうまい具合に重なる。
あれから、何があったろう。
20歳前後は、短期の仕事で稼いでは、北海道に戻って旅をする日々だった。旅の途中も、お金がなくなったら、その土地土地で働いた。雪が降り出す頃に、北海道を脱出し、紅葉と共に本州を南下し、また都会に戻った。

美瑛の丘 愛車スティードと共に
そんな暮らしが数年続いた頃。
地元の同級生たちは、社会人として、どんどん立派になっているように見えた。
ある日、稚内のノシャップ岬で決意した。
「旅から、足を洗おう」。
関西に戻って働き始めた廣瀬は、旅仲間になかば強引に、北海道に連れ戻されることもあったが、次第に都会の生活に慣れていった。
90年代のクラブカルチャー全盛の頃。出入りするようになった大阪や京都のクラブで、次第に運営側に回るようになり、イベント企画やプロモーションのようなことを始め、独学でフライヤーを作ったり、映像アーティスト(VJ)として活動した。これを機に、商業デザインに興味を覚える。デザイン会社に潜り込んだり、某大学のインハウスデザイナーとして経験を積んで5年。クリエイターとして、仕事ができるようになっていった。専門的にデザインを学んだことはないのに、本質を突く廣瀬の仕事は、業界で高く評価された。

先の尖ったピカピカの革靴、ブランド物のジャケット、撫で付けた髪の毛。
クリエイターにとって、洒落たパーティーに招待されることがステイタスでもあった。廣瀬も、その中にいたが、セルフブランディングに躍起になっている人たちと飲んで、よく喧嘩した。
「このグラフィックどう?上手いでしょ」
「うーーーん…上手いってなに?」
「このタイポグラフィの良さ、わかる?」
「うーーーん…でも、それで伝わってる?人集まったの?」
「デザインの役割というのは必ずあるのに、当時のデザインの在り方には、違和感があった」。
北海道で地方の豊かさを痛感した廣瀬は、独立当初、目指す「暮らし方・働き方」のビジョンをはっきりと持っていた。
ゆくゆくは都心ではなく和歌山あたりの田舎に、古い工場を改装して広いオフィスを持つこと。
みんなが思い思いの場所で、自由に仕事をするスタイルをとること。
オフィスを一歩出ると、そこには畑や川があって、畑いじりや、釣りを楽しみしながら、世界に通じるデザインをすること。
今でいうコワーキング、ワーケーションが定着する20年も前のことだ。美容師に憧れた頃の個室対応のお店のように、自らの中から湧いてきたイメージだった。
そして、2011年3月11日。
東日本大震災があった。
クリエイターの間に、ふるさとや、思い入れのある大事な「まち」と自分との関係を見直す動きが小さく生まれた。仕事を離れて、クリエイターが自分と向き合い、まちへの思いを小さな冊子にする「マチオモイ帖」の活動が始まる。
当時、廣瀬は大阪のデザイン業界にいて、「わたしのマチオモイ帖制作委員会」の最若手として活動に加わった。普段は、広告やプロモーションなど、商業的な仕事を受けるクリエイターたちが、街や自分に向き合う。「僕らの能力って、社会を変えることもできるんじゃないか?」と、感じるようになった活動だった。

大阪から始まったマチオモイ帖は、全国を巻き込み、2012年2月、クリエイターの憧れでもある東京ミッドタウン デザインハブでの大規模な展覧会に発展した。
東京ミッドタウン・デザインハブ特別展「my home town わたしのマチオモイ帖」は、会期17日間で7400人以上が来場、デザインハブの展覧会の中でも大盛況だったという。
デザインハブは、クリエイターにとっては憧れの地。廣瀬は、現場の空間設計や什器制作、展示システム、WEBサイト構築など、裏方の仕事に徹した。作品のぬくもり、マチオモイ帖の世界観が感じられるよう、ペンダントライトをアイキャッチに、シンプルな木のテーブルや布を使った空間デザインは好評を博した。
10年経っても忘れられない会話がある。このオープニングパーティーでの出来事だ。
クリエイター憧れのデザインハブで、大仕事をやり遂げ、廣瀬は天狗になっていた。
会場で、ITベンチャー「ダンクソフト」の副社長、渡邉徹さんと出会った時の会話、
「神山町って知ってる?いまSO(サテライト・オフィス)の実証実験やってるんだ。
古民家のこたつに座って開発したり、神山の環境を楽しんだり」。
10年前に描いたビジョンとピッタリ重なった。
この瞬間まで廣瀬は、社会のトレンドに巻き込まれ、東京で天狗になっていた。
今の自分は、どこに向かっていたんだ。やりたかったことを何もできていない。
まさか、このタイミング、六本木のど真ん中で、
自分のビジョンを思い起こすことになろうとは、まさに青天の霹靂だった。
この日を境に、廣瀬は自分を取り戻す。
パーティーから2ヶ月後、神山を初訪問した廣瀬は、6ヶ月後にはもう引っ越していた。
当時40歳。
「独立して10年、社会の大きい渦の中で、揉まれて、自分を失っていこうとしている中だった。
その時、”お前、そっちじゃないだろう?”と神山に引っ張られた感じがします」
古民家に引っ越して、地域の人とつながると、おすそ分けをたくさんもらった。
「野菜、もってけ!お返し?お前、そんなもんいらん!」
廣瀬が過ごしてきた消費社会とは全く違う、あの時、旅で見た地方の豊かさが、ここにある。
神山では、毎日がキャンプのようだ。
相変わらず、仕事は忙しかったが、
薪ストーブで暖をとり、川や湖で釣りに興じている。
思い描いていた暮らし方、働き方だった。
豊かな自然環境だと思っていた神山。
暮らしてみて、初めて気づくことがある。
町を流れる鮎喰川の水が、3分の1まで減っているという。
神山町に全体に広がる針葉樹の山々は、高度成長期に作られた人工林。
単層林に変わったことで、森林の持つ水源涵養をはじめとした公益的機能が失われつつある。
儲からないという理由で、切らなくなった杉は、
戦後70年を迎え、いよいよ大きな影響を及ぼしている。
水が無くなったら、神山に住めない。
どんなに神山が好きでも、住めない。
地方創生を進めたとしても、水が枯れたら、住めない。
一番、解決しないとならないのは、人口減少よりも環境だ。
同じことが全国で起こっているはずだが、ほとんど着目されない。
環境の問題は大きすぎる。
町民ですら、諦めている大きな問題だ。
「この真っ黒なオセロの盤面をどうひっくり返すか?」。
廣瀬は考えた。
杉の新しい価値を見出し、杉の利用を広げよう。
森と人の循環を創造し、社会の行動変容へ繋げよう。
2013年、神山しずくプロジェクトは「そんなもんできるわけがなかろう」という嘲笑の中で生まれた。
SHIZQのカップで利益を出すことが、最終目的ではない。
カップは、活動のアイコンとして、山林と水源への気づきをもたらすためのもの。
神山しずくプロジェクトは、単純な「商品の販売」ではなく、社会に「意識変容」を促す”活動”なのだ。
「僕が最初のオセロの白だとすると、SHIZQのカップを持ってる人は、もう1枚の白なんです。
僕とその人との間にいる人も、白に変わる。
僕ひとりではできないけど、盤面を白く変えられる」
小さな力で、盤面をひっくり返すために、都会で経験したことを活かす。
ブランディングという名の反逆のプロパガンダだ。
ミラノ万博に出展したり、日本のGOOD DESIGN賞、イタリア国際デザインコンペのソーシャル部門で金賞を受賞したり、農水省と内閣府の賞を受賞したのも、はっきり言って、廣瀬の戦略である。10年経って、ようやく事業が回り始めたが、廣瀬は、神山しずくプロジェクトには投資するばかりで、対価はもらっていない。次の世代のために循環させることが目的だからだ。
廣瀬は、森や水源に対して、無関心な世の中を大きな湖に例える。
高度成長期、バブル経済、リーマンショック、コロナ、紛争、
いろんなものが撹拌され過ぎて、何が大事なのか見えなくなった社会は、
「思考停止」「無関心」な、まるで凪の湖。
そこに、一滴の”しずく”を垂らすことで、波紋を生みたい。
この”しずく”の純度が、高ければ高いほど、社会に広がるんじゃないか。
だから、活動の純度を高くすることにおいて、SHIZQは妥協したくない。
SHIZQのメンバーは、毎年冬の伐採期、山に入って、自分たちで木を伐る。
鮎喰川の支流の水を引いた田んぼで、無農薬の米を作る。
SHIZQの職人は、地元の炭を使って鍛治仕事で刃物を作る。
ミシ..バリバリバリ!ドッシンッ!
廣瀬は、初めて木を伐った時、直感的に気付いたと言う。
「木は”生き物”だったんだ。命をいただいている」
木を伐ることで、一帯の環境が変わる。
「全部、繋がっている」。
だから、神山しずくプロジェクトでは、伐った杉を余すことなく使う。
これでもか、というくらい、一貫した哲学で動いている。
「マーケットはそこにはない。
SHIZQは、ゼロからマーケットを作っているんです。
僕は、希望をデザインしている。
実は、何度もやめようと思ったけれど、
SHIZQを始めてからの僕の10年は、そこに希望があるから続けてこられた。
小さくていいから、若い世代に、いい感じのバトンを渡していきたいんです」
振り返ってみると、廣瀬には10年ごとに人生の節目があるようだ。
20歳の北海道、30歳でデザイナーとして独立、40歳の神山移住、そしてSHIZQ10年目の50歳。
社会のパズルに、自分のピースがハマらず、自分を持て余していた10代。
北海道の旅で、廣瀬圭治という独自の方程式を持つピースが生まれた。
その方程式を社会に試すように訓練をしていたのが、30歳をまたぐ大阪での10数年だった。
そして、神山に出会い、方程式の原理に合わせて、行動を起こしたのが40歳からこれまでだったのだろう。

スティードの頃は、若くて自由、軽快なエンジン音で走っていた。今は、ハーレーの重みのあるエンジン音が、しっくりくる。実はこのハーレーは、創業100周年記念モデルの2003年製、廣瀬がデザイナーとして独立した年に作られた。北海道から戻って、迷いながらも自分で道を切り開き始めた年。不思議な縁、タイミングを感じる。
旅の最終日、ふと思い出してSpotifyでスマパンの「Siamese Dreams」を呼び出した。バイクで走りながら聴くのは、本当に久しぶりだ。
1曲目の「天使のロック」で
イントロから、涙が溢れてきた。
2曲目の「Quiet」の疾走感で、
アクセルを開ける。20歳の自分が蘇ってきた。
3曲目の「Today」で、広大な青空と一本道の風景と自分が一体に。
「武装解除」「宇宙兄弟」、当時のことが走馬灯のようにめぐる。
最後の2曲「Sweet Sweet」「Luna」で次第に気持ちが落ち着き、周りの景色を見る余裕が生まれてきた。
なぜ、廣瀬は、50歳というタイミングで、北海道に再び戻ったか?

廣瀬の持っていたパズルのピースは、20歳の北海道で解き放たれた。
パズルの穴に嵌め込まれることから、自由になり、自分の核となる生きる姿勢、明確な美の基準が形成された。
結果的に、廣瀬の中の「核」が蠢き続けた結果が、今の神山しずくプロジェクトだったとも言えるだろう。今、廣瀬は、炎の玉のようにエネルギーをまとったピースを、社会というパズルの大きな枠そのものに投げかけている。
「その価値観は、本質的なのか?」
「思考を、止めるな」
「行動し続けろ」
廣瀬の投げかける提案や想いは年々、重く大きくなっているが、共感してくれるスタッフやファンも沢山居る。
「これまで暗中模索しながら
信じてやってきたことで
より深く将来の在るべきビジョンが見えてきました。
今度は、そこに向かって一歩踏み出そうと思う」
2023年7月。
神山しずくプロジェクトは、10周年を迎える。
廣瀬のこれからの10年は、今はじまったばかりだ。
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=A3fq-reBSVw]